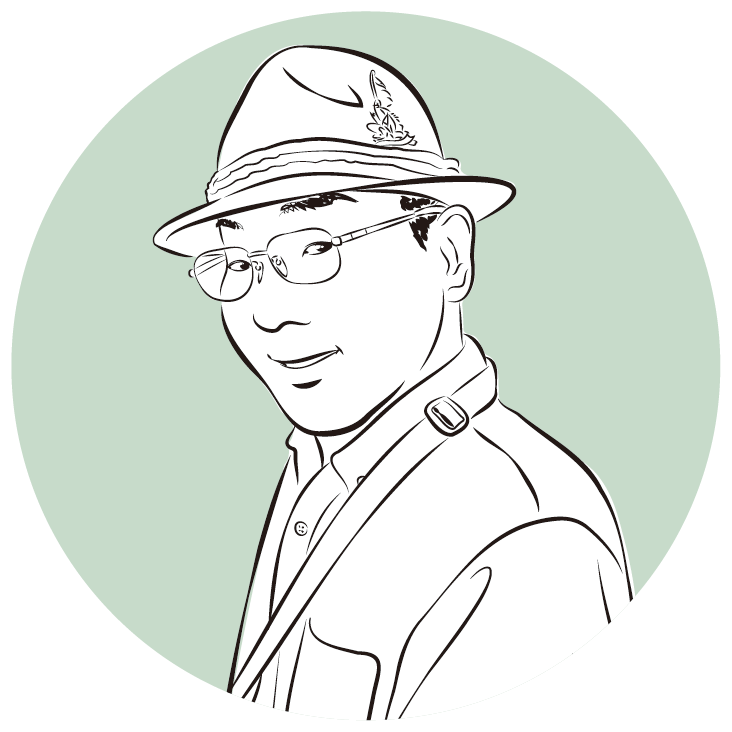クルマ作り以外に見える一流の証
世界最高級の乗用車ロールス・ロイスはイギリス・グッドウッドに本社があり、隣接の工場で生産されている。BMWグループに属してからはボディとエンジンはドイツで生産、ドーバー海峡を渡って英国に運びこまれ、専用工場のグッドウッドで塗装とアッセンブリーが行われている。
世界最高級車の誉は創業時以来続いている。それは製作者ヘンリー・ロイスが自動車工学に貢献し、品質というものを再評価した事に端を発している。ロイス以前の品質とは塗装や飾りなど、表面的な事に関する漠然としたものであった。しかし、彼は品質の定義を機械的完璧さとし、申し分のない性能と伝説となった信頼性を兼ね備えたクルマ、1904年に第1号車(2気筒・10馬力)を製造し、自動車の新しい基準を示したのである。
この1号車が当時の自動車の中では、より扱いやすく、静かで信頼性があり、洗練されていた。そして、このクルマにほれ込んで援助した人こそ「チャールス・スチュアート・ロールス卿」。企業家としての才能を発揮し、ビジネスマンのクロード・ジョンソンと共にロールス・ロイス社の名声を不動のものにしていった。
当時、ロールス・ロイスに乗るような人物は、少なくともヨーロッパではまさに衣・食・住がロールス・ロイス級のレベル。ロールスは生活に溶け込んでおり、サイズに見合う大きいガレージで、常に磨き上げるショーファー(運転手)がいるのが自然だった。
彼らは、週末には思い切り着飾ってパーティに出かけ、新調したドレスやタキシードで引き立てる。そして、パーティ自身に重みを付ける、いわば演出の小道具としてロールス・ロイスは不可欠な存在であった。
そんな1930年代、自動車が技術的にも趣向的にも抜群の発育を示し熟しきったヴィンテージ時代に一風変わった高級車造りが始まる。それはボディを注文で架装し、好みの内装を施してくれる「コーチワーカー」。ロールス・ロイスだけでもブリュースター、H・J・マリナー、パークウォード、フーパー、フリーストン&ウェッブ等の一流コーチビルダーが活躍した。
上流社会にふさわしい品質と気質
そんなロールス・ロイスの名は、優秀な品質の代名詞として使われるようになる。その高品質は並み大抵なものでないと聞かされ続けていく。同社のシルバーゴーストは一生買い替える必要はないなどとも。
「タイヤとガソリンの種類が、いつまでこのクルマ向きに作られるかが、このクルマの寿命を大きく左右することになるだろう」。これはシルバーゴーストを作り上げたエンジニアに与えられた最大の賛辞だった。シートに使われているコノリーレザーは「クルマが腐ってしまっても、本革だけは残る」と言われ、もし、間違ってクルマが燃えるようなことがあっても「我々の仕事だけは残る」とコーチワーカーの方も負けてはいない。お互いに自信満々の職人気質の言葉が、ロールス・ロイスの実力を物語っていたのである。
昔はやたらな人には、クルマを売らない方針があったとまで聞かされた。その代わりに一度注文を受けるとなると、徹底的に面倒を見てくれたという。クルマの仕様はもちろんの事、お抱え運転手の教育までもの徹し方。上流社会のマナーは実に厳しいものだし、格式にこだわるのも当然であったのだ。
16万キロ走行を保証するエンジン組み立て
当時、英国の中都市クルーの郊外にある古い工場では、まずオーナーのフルネームを記した本革張りの表紙に包まれた1冊の単行本から、ロールス造りが始められた。これがロールス・ロイスの1台のヒストリカルブック。そこには注文した仕様をはじめ内張り、カーペット、ウォールナットの材質、色調、組み立ての進行状況等が克明に記入されており、取り扱い説明書にもなっている。
そして、エンジンの細かいパーツは高精度な最終検査をパスした後に組み上げられ、ベンチテストの上で天然ガスを使って、少なくとも240km以上の走行テストを実施。ここでは検査員が医師の如く聴診器をつけ、人間の耳では聞き取りにくいほど微妙なノイズの変化を聞き出す。しかも、彼がもし気に入らなければ、せっかく長時間かけて組み立てたばかりのエンジンは情け容赦なく工場に返送される。
この検査をパスした100台のエンジンの内1台がピックアップされ、ガソリンを使ってまた8時間フル回転のベンチテストを実施。この選ばれた1台のエンジンはすぐに分解され摩耗の状態を検査し再び元に組み立てられる。これこそがカタログに「ロールス・ロイスのエンジンは定期検査以外に注意を払う事なく、少なくとも16万km走行可能に設計されている」と書かれている所以である。
また、ロールスの有名な広告コピーには「毎月5日、2人の専門家がイタリアのロンバルディ平原に出かけて行く。そこで次の12か月の生産に使われるパネル張り用に1本のクルミの木を選んでくるのだ」とある。この丸太からまるでお菓子のウエハウスの様に、薄い板を造形。化粧張り板は上質のラッカーで2重、3重の防護塗装がなされ、低温炉の中で1日かけて硬化される。
ロールスの場合、ダッシュボードのウッドフェシアは中央で左右の模様が全くシンメトリー(対称)になる様に、実際に鏡を使って注意深く裁断されたと伝えられている。
シートの本革も品質にこだわり独自飼育の牛から
家具に使用するにしても、労働を重ねた牛は皮が硬くて向かないとされている。ロールスの下請けである皮屋コノリー・ブラザーズ社も牛を飼育するが、皮を綺麗に仕上げる為に、牛を傷つけない様に牧場の柵に電流を流した特別な施設で飼育。また、上質の皮を育てるには食料も思い切り吟味され、牛にビールを飲ませたり、良い音を聞かせている。皮シート生地は高級車になると牛の育て方まで違ってくるわけだ。
また、ロールスに使用されている内張りは約23.4m2のコノリー・ブラザース社製の「最上級英国本革」を使用。しかも約500枚のうち、たった1枚だけがロールス用として選ばれ、残りは高価なハンドバック用として送り返さると言われている。数多くの熟練した内装職人達は、それぞれのシート用の革と色のキメが完全に合っていなければ決して作業をしたがらない。正に「職人魂」だ。
ロールスの静粛性は古くから語り継がれてきた。「如何なるスピードで走行しても、時計の音が一番高い」。即ち、超高精度で仕上げられたエンジンはもとより、細部を念入りに造り上げた結果、この静粛性に達したのである。ボディの如何なる細かいメタルの継ぎ目ですら、パテできれいに埋め込む。フロアには厚い防音層がたっぷり張りめぐらし、ウイルトンのパイル・カーペットが敷き詰められ、この上にさらに子羊のカーペットを敷き詰めるのだ。
さらにサウンドとしてエキゾースシステムは少なくとも4つの吸音器(マフラー)を取付。このマフラーは各々が異なった周波数の音を吸収する様に調整されているほか、電動パワーウンドウはナイロンのスプロケットを特注して、ウインドウの開閉音を減じるなど、徹底した異音対策が施されている。
ロールスの象徴となったフライングレディ
ロールスの有名なマスコットといえば、ラジエーターグリル上のフライングレディである事は言うまでもない。「恍惚の魂」と名付けられた像のオリジナルデザインは、1911年に英国のチャールズ・サイクスの手で造り出された。
ラジエーターグリルは当時、全て手造りでひとりの職人が約1日半もかかって造り上げたと言われている。しかも職人は定規ひとつ使わず、良質のステンレス・スチールの平板から仕事が始められた。そのため、グリルの表面は決して直線ではなく、かすかに弓形に曲げられており、建築家はエンタシスと呼んでいる。
同じ原理がカリクラテスのデザインしたギリシャのパルテノン神殿に使われている。各々の面がトータル的にバランスをうまくとり合って、グリルの形状に収まった時に抜群の剛性と美しさを構成。組み立ての終わったロールスは大勢のスタッフの待つテスト部門に送られ、うち数十人がロードテスト担当。最終検査は20年以上の経験を持つ2人のテスターが25~240kmもロードテストを実施するそうだ。
そして、無駄なノイズを見のがさない彼等の「お得意作戦」は、トランクに潜り込み、真っ暗な中で静かな音の診断を行うというもの。また、塗装の仕上げも再度行われ、特殊な高出力ランプの機械で、ボディ表面の小さな欠陥・傷も見逃すことはなく徹底している。前述の本革表紙のオーナーズブックにチーフテスターがサインすると、はじめてロールス・ロイスが完成する事になる。
ロールスロイスに関する言い伝え
ロールス・ロイスには品質とアフターサービスと気位の高さを良く言い表した伝説がある。また各モデルに付けられたネーミングを例に出して、ロールス・ロイスは「化け物だ」と言う口の悪い人もいる。シルバーゴーストは幽霊、ファンタムは妖怪だし、レースは生霊だと。これは音の静かな事でもたくさんの伝説を持っているロールス・ロイスだからこそ生まれた表現と言えるのではないのだろうか。イギリスの霧深い中から、音もなく現れて出て来る大きなロールス・ロイスに出くわした時の気分お分かりだろう。
「わが社は絶対に悪いクルマを造るわけがない。何故なら門番が悪いクルマじゃ外に出さないはずだから」。車内のテーブルに水を八分目入れたコップをおいて数百マイル走ったが一滴もこぼれなかった。
なお、アフリカの砂漠でシャフトが折れたので電報を打ったところ、ヘリコプターが部品を積んできてすぐ修理をしてくれたが、その代金をおそるおそる聞いたところ、返事はこうだったそうだ。「いや無料です。ロールス・ロイスには故障というものはございません。」
いずれも、どこまで本当か疑わしいが、語り継がれている伝説である。
※参考文献:ロールス・ロイス(ワールド・カーブック)、Winds(ロールス・ロイス特集)、The 高級車(モーターファン)
撮影協力:GLIONミュージアム