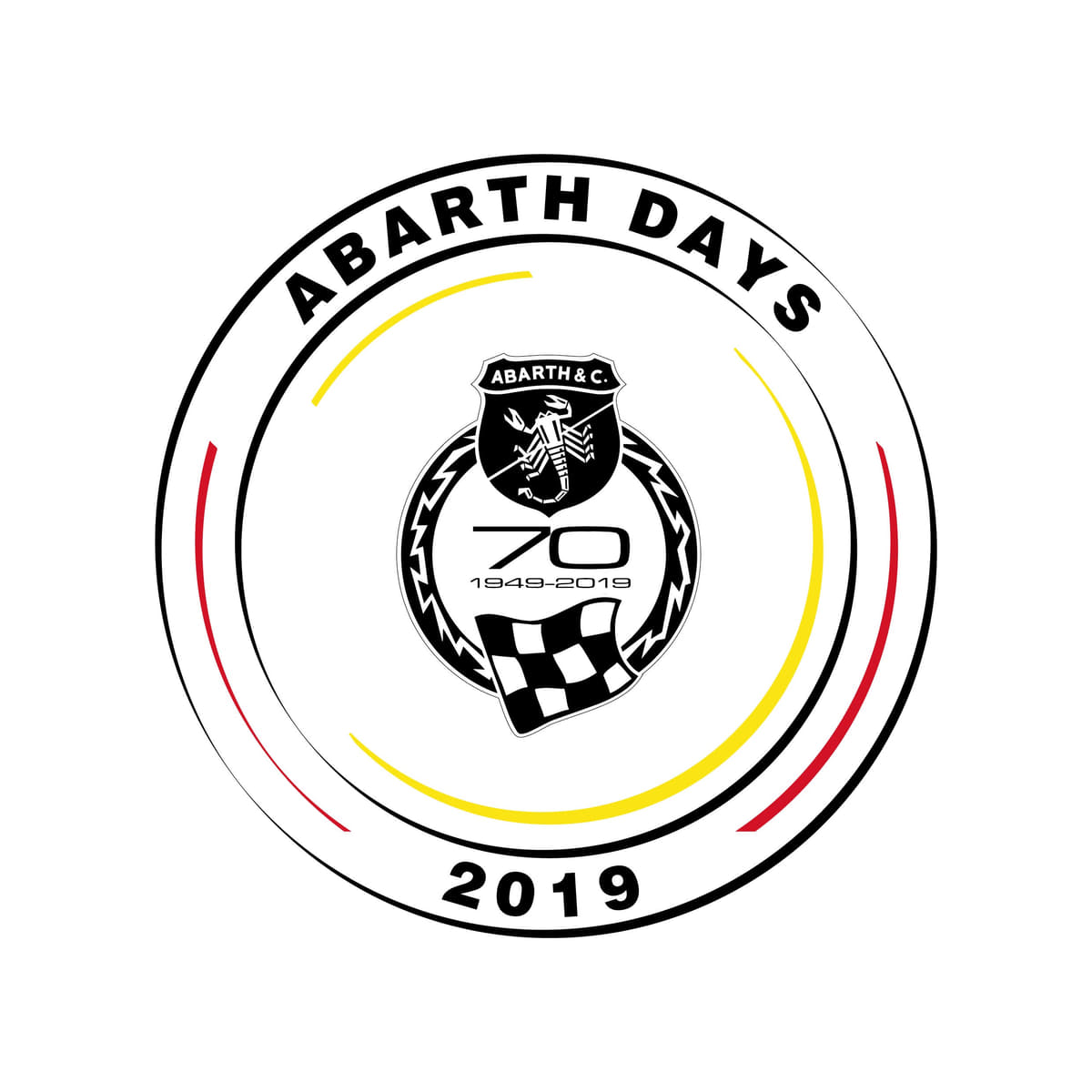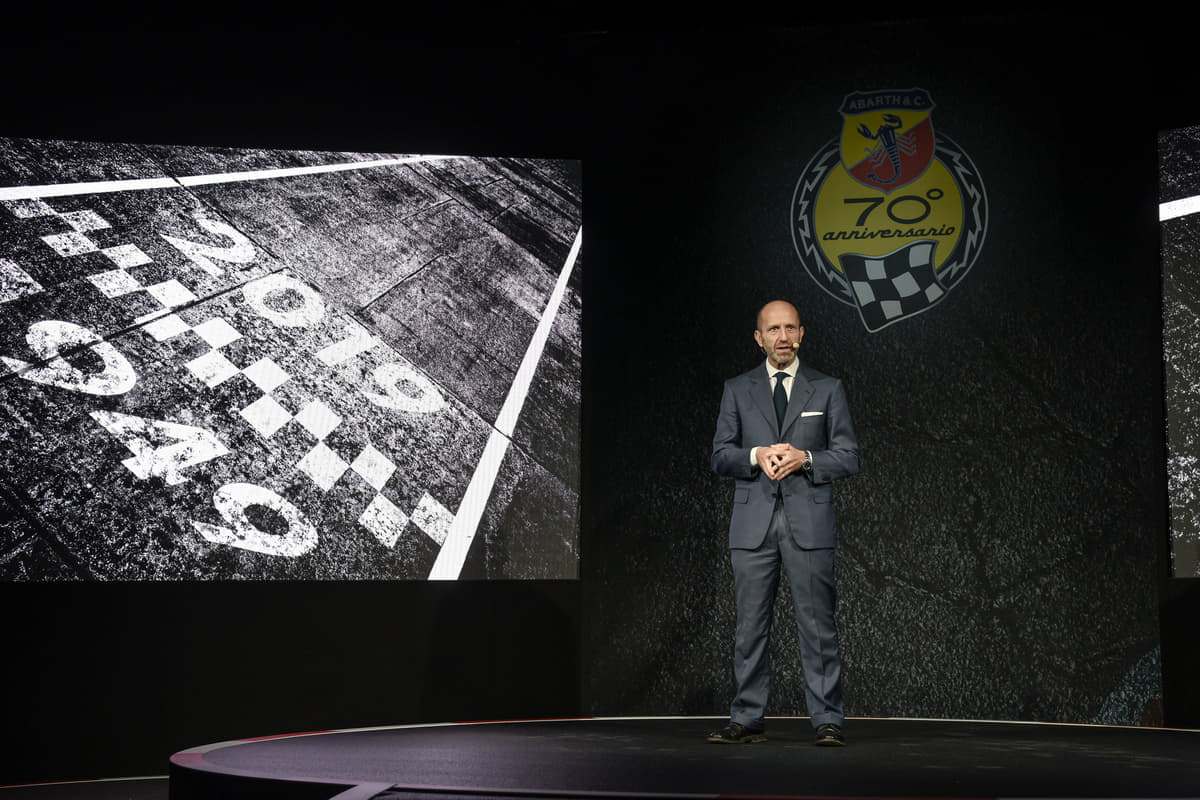メインコンテンツはアバルトらしい“走り”だった
カルロ・アバルトという自動車史に名前が刻まれた稀代のチューナーが自らのファクトリーをおこしたのは、1949年のことだった。2019年はアバルトにとっての70周年のアニヴァーサリーイヤーだ。世界各国でそれを祝うイベントなどが行われ、日本でも11月9日に富士スピードウェイを舞台に、“アバルト・ディ”の名のもとで大々的なイベントが開催された。そちらについてはこのオートメッセWEBでもすでにレポートされているが、それに先駆けること約1ヶ月前の10月5日と6日の2日間、実はイタリア本国でも“アバルト・ディズ2019”というイベントが開催されていて、僕はその会場にいた。ちょっとばかり時間が経ってしまったが、アニヴァーサリーイヤーのうちにレポートをお届けしておきたい。
会場となったのは、ミラノ・エキスポの会場跡地であるMINDことミラノ・イノヴェーション・ディストリクト。ここに集まったのは3000台を超えるアバルトと5000人を越えるユーザーやファンだ。アバルトのイベントとしてはおそらく世界最大級で、過去のどのアバルト・ファンの集いをも上回っているという。70周年を祝うのに相応しい、喜ばしい記録である。
昨年はヨーロッパの7箇所で開催されたアバルト・ディズだが、その会場は全てサーキットだった。今回はミラノの市街地での開催となったのだが、さすがアバルトらしいぞ! と感じたのは、それでもメインとなったコンテンツがやっぱり“走り”であったことだった。エキスポ会場跡地の広大な敷地にある取り付け道路や駐車場を利用して、3km近い長さの特設クローズドコースを作り上げていたのだ。
一般的なサーキットのように複数のクルマをランダムに走らせて抜きつ抜かれつのバトルなんてことはできないし、低中速コーナーが主体となる速度域が低めのコース設定だったけど、コースレイアウトそのものは変化に富んでいて、加速力と減速力、荷重移動の様子、低速&中速コーナーでのハンドリング特性をチェックしたりするには充分。思いのほか攻めた走りを楽しむこともできたのは見事だった。
参加者達はここに自分のアバルトを持ち込んだり、あるいはメーカーが用意していたアバルト最新ラインナップをテストすることができたのだ。最新ラインナップについては一般道で乗り味に触れられるコースも用意されていて、いずれの受付場所も常に黒山の人だかり状態。アバルト好き=走り好き、を証明していたようなものだった。試乗者は2日間トータルで3500人を越えたというから驚きである。なるほど、こういう国だからこそアバルトのようなブランドが生まれたのだな、と妙に納得させられた感じだ。
特設コースは別にもうひとつ設けられていて、そちらではラリーのR-GTクラスを戦う124ラリーの同乗試乗がひっきりなしに行われていた。実際に124ラリーで競技を戦っているプロのドライバーが操るマシンの助手席で、静止状態からの全開加速、ストレートからのブレーキングでリアをスライドさせながら直角ターンへと入っていくときの姿勢変化、ドリフトしながらの360度ターンとそこからの全開加速などを体験することができ、124ラリーが市販の124スパイダーとは全く別物といえる速いクルマであることや、腕の確かなドライバーが操縦すると車体が極めて正確に反応するということを、存分に理解することができた。
加えて、一定以上のGがかかるとタイヤが滑り出す特別な仕立てのアバルトでクルマが不安定な挙動を示したときの取り扱い方をインストラクターがレクチャーするコーナーが用意されていたり、ドライビングシミュレーターのコーナーが用意されていたり、と目につくのは“走り”にまつわる催しばかり。
それはそれで楽しいからいいのだけど、ふと思ったのは、“70周年”を記念する年のイベントなのに自らの歴史にまつわる催しはどうしたのだ? ということ。アバルトの歴史的な名車がほんの3~4台、トリノのヘリテージHUBから持ち込まれて並べられていたが、ぶっちゃけ、それだけだった。かつてのモータースポーツにおける華麗な戦歴に光を当てるような何かがあったわけでもない。その辺りは日本のイベントの方が、比較にならないぐらいに充実していた。思い切り肩透かしを喰らった気分だった。
が、彼らには彼らのリスペクトの表現方法があったのだな、と今では思っている。展示だとか何だとかより、“アバルト=走る楽しさ”という黎明期からの伝統にフォーカスしてアニヴァーサリーを祝うのも、歴史に対する立派なリスペクトだ。それに次の第2回レポートで触れる、このイベントで初めて一般公開された
“695セッタンタ・アニヴェルサーリオ”というスペシャルエディションに巧みに盛り込まれていた、たくさんのオマージュだってそう。イタリア人ほど“今”を楽しむことに長けた人達はいないわけで、歴史とともに“今”をきっちりと楽しみ尽くすことこそ、イタリアらしい感覚なのかも知れない。そんなふうに感じている。