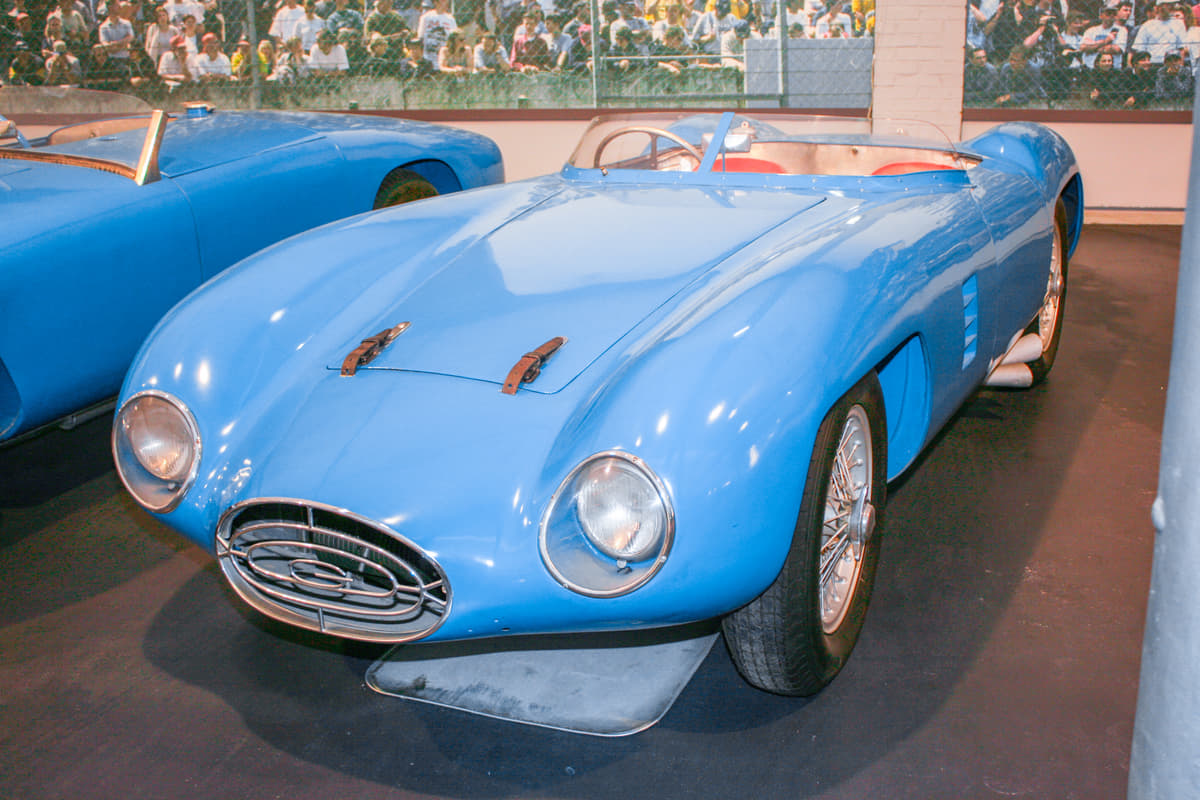フランスのエンジンチューニングの匠
ルノーのトゥインゴやクリオのスポーティモデルのグレード名とし
さらに時間を遡っていくと、第一次世界大戦後に創業者であるアメディ・ゴ
ル・マン24時間で大活躍したゴルディーニ
19世紀末の1899年に、イタリア北部のエミリア-ロマーニャ
そもそもシムカは、フランスにおけるフィアットのインポーターからコンプ
そして、
ルノーと提携しハイパフォーマンスなカタログモデルをプロデュース
シムカとの提携を終えたあとも、単独で5シーズンに亘ってF1GP
そして翌1957年には初のカタ
その8のハイパフォーマンス版がR
まだ世界選手権ラリー(WRC)が制定
アルピーヌのエンジンチューンと世界最初のワンメイクレース
1956年にルノーと提携し、ルノーのハイパフォーマンス・モデ
1963年には初作のA210/M63を3台エントリーし
このレースからは、1976年のヨーロッパF2チャ
ルノーはその後、1973年にはアルピーヌをも買収していましたが
このように歴史を振り返って