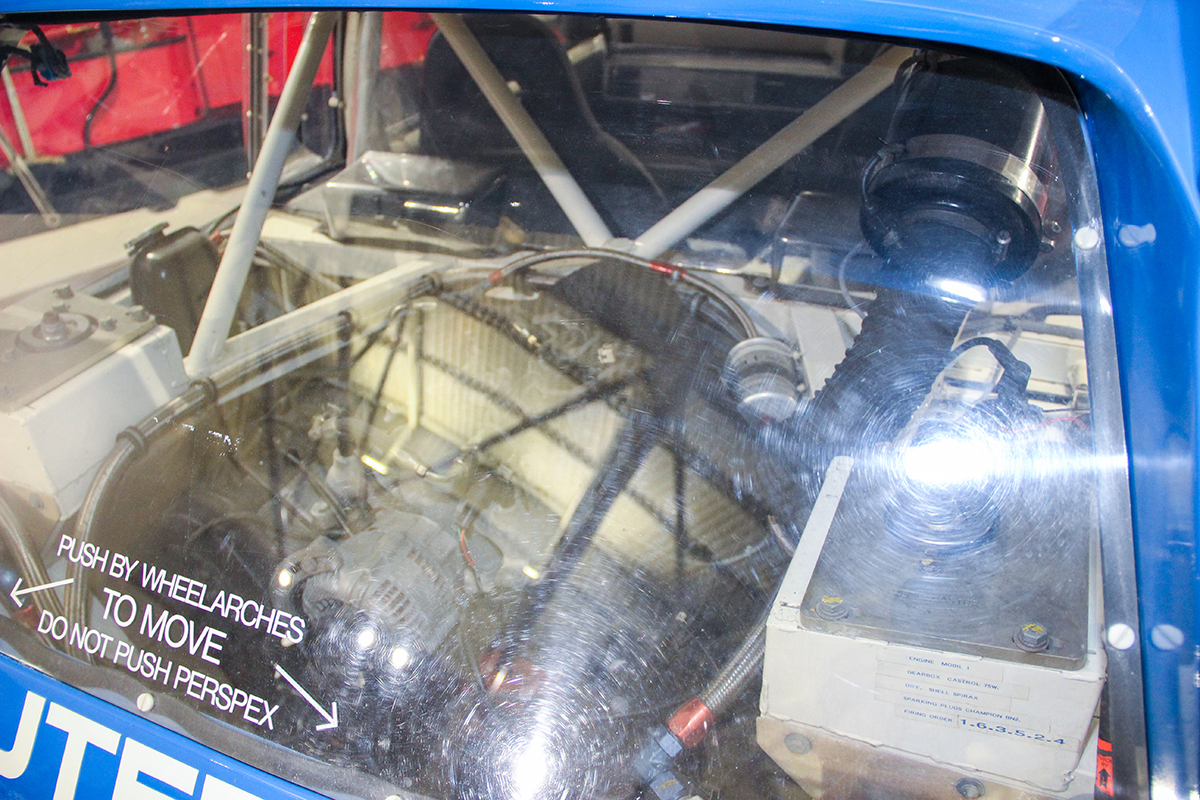WRCで勝利するために開発されたマシン
1970年代終盤から1980年代初めにかけてブームが巻き起こったスーパーカーたちは、揃ってエンジンのミッドシップ・レイアウトを採用していました。F1GPを筆頭に、モータースポーツの世界ではミッド・エンジンが当たり前で、理論的にもハンドリングが優位になることは証明されていました。“ミッドシップ”は流麗なボディとともに、スーパーカーの必須アイテムとなっていたのです。
その一方で、フィアットX1/9やロータス・ヨーロッパ、マトラ・ジェットなどのように、前輪駆動(FWD)のパワーユニットを、そのままミッドシップに移植したライトウエイトスポーツカーもいくつか誕生していました。
そんななか、FWDの2ボックスハッチバックをベースに、ミッドシップのスポーツカーに生まれ変わったのが1980年のブリュッセル・ショーでデビューしたルノー5ターボでした。今回は、大衆車をベースに怪物へと昇華したルノー5ターボを振り返ります。
庶民の足としてデビューしたルノー5がWRCで活躍
ルノー初のFWDとして1961年にデビューしたルノー4(quatre=キャトル)。その後継モデルとして1972年にデビューしたルノー5(cinq=サンク)は当初、エンジンこそキャトル由来の直4OHVで、ベースモデルのLにはキャトルと同じ782cc/34ps版が搭載されていました。輸出用には845cc/36ps版が、高性能版のTLには956cc/43ps版と3タイプが用意されていましたが、ボディは3ドアハッチバックのみでした。
もっとも、1979年のマイナーチェンジの際に5ドアハッチバックが追加されることになりました。それはともかく3ドアハッチバックというと、まったくベーシックな、いわゆる“足グルマ”と捉えることもできます。その一方でスポーティなクルマ、という捉え方もできました。
高性能版まで用意したことから、ルノーでは後者の考え方だったろうと思うのですが、実際のところ1974年には1289ccエンジンを搭載したLSが追加され、さらに1976年にはホットバージョン、1397cc/93psの直4ユニットを搭載したルノー5アルピーヌが登場しています。そして、その考えを裏付けるように、ルノーはワークスチームを組織して世界ラリー選手権に参戦したのです。
技術向上を目的に創業当時からさまざまなモータースポーツ活動を続けてきたルノーは、戦後はドーフィンなどのベーシックカーで熱心にラリーを戦っていきました。1973年にはアルピーヌを買収してモータースポーツ専門子会社のルノー・スポールを設立、ルノー5にハイパフォーマンスなアルピーヌ仕様を登場させ、若手ドライバーだったジャン・ラニョッティを擁してWRCへの参戦を開始。
ラニョッティはみるみる頭角を現すようになり、1978年のWRCシーズン開幕戦、モンテカルロ・ラリーではポルシェ911RS3.0のジャン-ピエール・二コラに次ぐ2位でゴールイン。3位にはチームメイトのギ・フレクランが続き、ルノー5アルピーヌは、見事2-3フィニッシュを飾ることになりました。排気量が倍近いスポーツカーのポルシェに、わずか2分弱の差で、高性能バージョンとはいえFWDの3ドアハッチバックが続いていたのですから、これはもう快挙というしかありません。しかし、FWDで戦うには限界があったのもまた事実でした。そこで次の一手が考えられました。