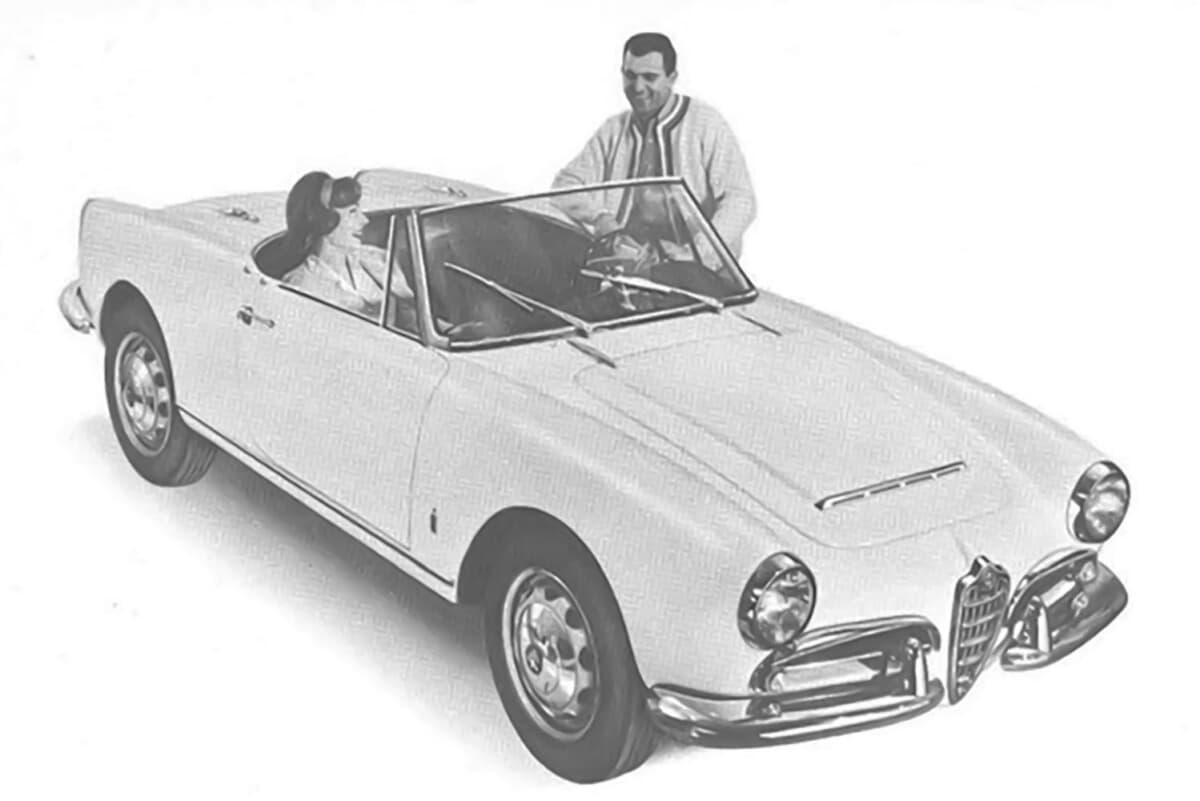『ウィーク・エンド』:クルマ=物質主義の狂騒と炎上
1950年代末から60年代初め頃は、ヌーヴェル・ヴァーグ一派ではないもののルイ・マルが『死刑台のエレベーター』でメルセデス・ベンツ300SLを効果的に挿入したし、スピード狂だった作家のフランソワーズ・サガンはタルボ・ラーゴT26グラン・スポールに乗っていた。ようはまだ、クルマが自由や解放をもたらす何かで、芸術家たちも特別なクルマにインスパイアされた時代だった。とはいえヌーヴェル・ヴァーグの若手監督たちは、ドアを外したかキャンバストップを下ろしたシトロエン2CVに、カメラをかついでハコ乗りするのが定番だったらしいが。
そんな牧歌的な時代が過ぎて、芸術家肌には生きづらい文明と社会の退廃をシニカルかつ悪意に満ちた視線で描いたのは、ゴダールの1967年作『ウィーク・エンド』(原題/Week-end)。老親の遺産を狙う主人公のブルジョワ夫婦がある週末、渋滞が常態化したパリ近郊の路上を進みながら、ありとあらゆる事故や暴力を目撃する。
週末のレジャーのためなら、他人をアオる・排除する・蹴散らす・殺すことすらいとわない、あらゆる社会階層の交通参加者たちが、シトロエンDS19にルノー16や4L、オースチン850ミニMk.1やシムカ1000、パナールPL17らに乗って、あるいはそこから降りてきては、血なまぐさい争いを繰り広げる。
無論、クルマで出かけるというレジャーや、ほの暗い欲望に憑りつかれたブルジョワたちをカリカチュラルに見せているわけだが、今日の日本の路上の現実もけっこう遠からぬような……。数台のクルマが折り重なって炎上するシーンは、ゴダールの毒気がこれでもかと炸裂する。劇場公開後の評判は当然、最悪で、ゴダールが極左運動に決定的に身を投じる直前の1本となった。

『カルメンという名の女』:魔性の美女とホンダ・クイント
もうひとつ、ゴダール作品で記憶に残る1台は、10数年を挟んだ1983年、『カルメンという名の女』(原題/Prénom Carmen)。プロスペール・メリメの小説『カルメン』を下敷きに現代仕立てにした枠組みで、マルーシュカ・デートメルス演じるヒロインに、憲兵隊の警官だった若者が破滅的に恋焦がれてしまう。
そこで久々に男と女の逃避行のためのクルマが登場するのだが、フィーチャーされたのはなんと、ライトブルーのホンダ・クイント。アコードとシビックの中間モデルで、後のインテグラに繋がっていく、ぱっと見に素晴らしく凡庸な、あのころの日本車ハッチバックだ。パッションとはほど遠い、直線的で生硬なボディラインが、ヒロインのファム・ファタル(宿命の女)っぷりと恐ろしく好対照で、80sビューティーの破壊力を引き立てる。
ところで作中にはベートーヴェンの弦楽四重奏曲が頻繁に用いられているのだが、ホンダ・クイントまたはローバー名クインテットとは、5枚続きのカードの上がり手とか五重奏のことで、音との関係で意味深にも思えてくる。
* * *
いずれ、映像の意味や解釈はつねに後づけで観る者任せ、と監督はうそぶいていたが、まさしく巨匠の尖りまくった映像感覚は、いつぞや引用されていたアルチュール・ランボーの詩よろしく、永遠に再発見され続けるものなのだ。
いわゆる主人公に感情移入してRPGのように一体化して観て感じるみたいな、今どきの視聴スタイルにまるでそぐわない破天荒プロットがゴダールらしさそのものだが、直近の週末でもいつでも構わない、デジタルリマスター版DVDで観て後悔することは、決して多分、ないだろう。メルシー、ア・ビアントー、監督!