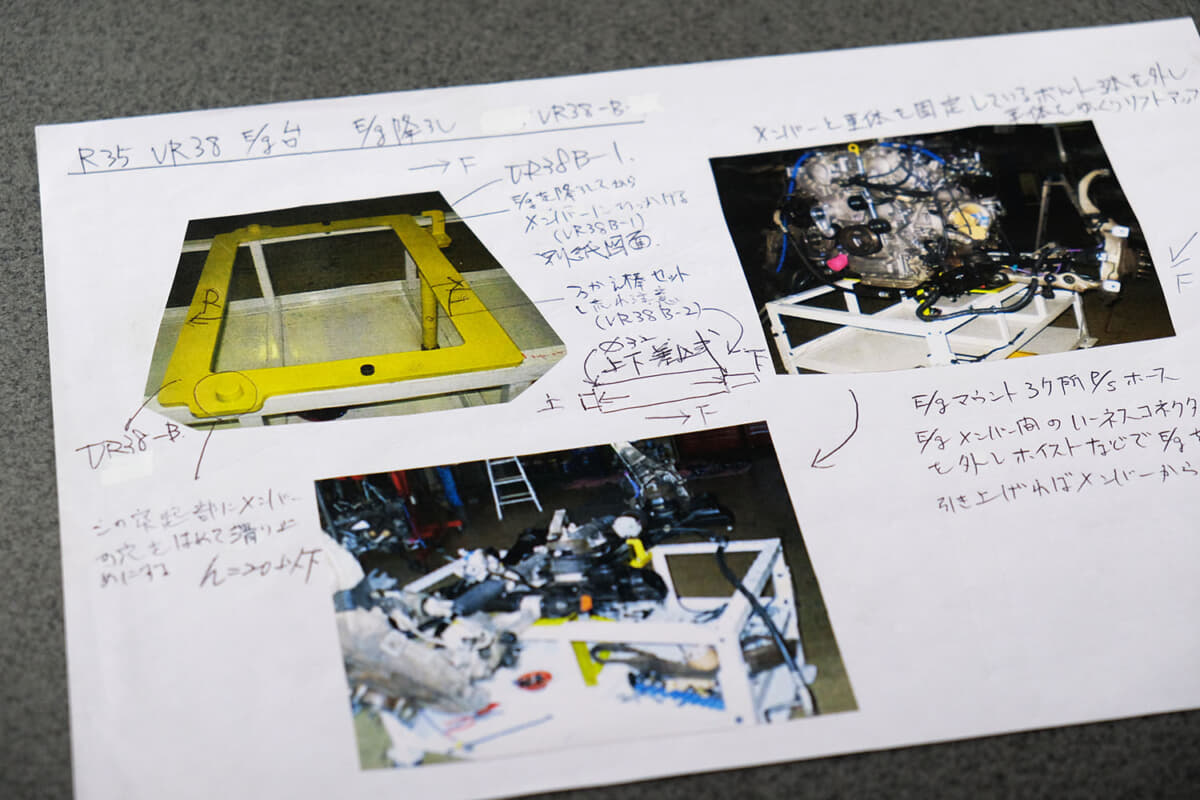数値では表現ができないフィーリングを重視する
ストリートゼロヨンとは一線を画す、本格的なドラッグレース用のマシンとしてR33GT-Rを変貌させる。そんな目標に向かってデモカー作りを開始した。
2.7Lキット、IN290度/EX300度のカム、それに二つのGT3037ターボとウエストゲートはいずれもHKS製だ。各気筒には720ccと320ccの二つのインジェクターをセット。吸気や排気まわりはワンオフ仕立てだ。制御系はHKSのVPSでエアフロレス化して、メインコンピュータの書き換えで対応する。この仕様でブーストを2.2kg/cm2かけて1000psオーバーの実力を発揮し、もはや測定不能の領域だ。
ゼロヨン競技に参加するとトランスミッションが音を上げた。Hパターンのドグミッションでは耐えきれず、シーケンシャルのホリンジャーを導入。トランスミッションが解決すると、今度は油圧系のトラブルが勃発し、ゼロヨンの加速中に油圧が途切れて一瞬でエンジンがブローした。ひと通りオイルパンの加工を施しての出来事だったのでショックは大きい。
ゼロヨン用にワンオフ製作した足まわりは、前が浮き気味で加速する。この特性がオイルの偏りを助長した。どうしたものか考えあぐねていたが、自分ではどうすることもできないのでHKSに相談して、レーシング部門のスタッフに教えを請うた。
エンジンの精度を出す組み方や、油圧維持のための加工方法などをショップに出向いて実践してくれた。作業自体は大きくは違わないが、ほんのひと手間をかけることで効果が思いのほか大きくなる。そんな貴重な体験を経てトラブルを克服し、1万1000rpm回してもびくともしなくなったR33は、指山代表のドライブでゼロヨン9秒3を成し遂げた。
余力をもたせたチューニングならユーザーも負担なく楽しめる
2001〜2002年はドラッグレースにのめり込んで、その後サーキットにも進出。エンジン仕様は同じながらも、ブーストを抑えてパワーを控えた。しかし、筑波サーキットはなんとかこなせるが、富士スピードウェイではエンジンが耐えきれない。400mを走り切ることに狙いを定めて仕立てたので、サーキットでの周回には無理があったのだ。
「サーキットやストリートでも楽しめるようにターボをTO4Zにして仕様変更したんです。これで耐久性は大幅にアップして、富士でも難なく走れるようになりました」
それが2003年の出来事だ。IN/EX共にHKSの280度カムに換えて、インジェクターも720ccとした。これでブースト1.5kg/cm2なら700ps前後をマークする。
「気負わずに走れてそこそこ速い。とくに乗りやすさを重視した味付けを目指しました」
絶対的なパワーよりもアクセルレスポンスといったフィーリングを徹底的に重視している。ピーク付近はシャシダイでセットアップして、途中の味付けを実走で詰めていく。数値では表現できない乗り味こそが、指山流の醍醐味なのだ。
「生涯で一番チューニングしたクルマがこのR33ですね。それにゼロヨンからサーキット、実走セッティング、さらには普段使いまで、走り込んだ距離も密度も断トツです。だからさまざまなことが学べました」
デモカーを100とするとユーザーカーは70〜80に力を抑えて余裕を持たせる。エスカレートするユーザーに冷静さを取り戻させることも必要だと気付かせてくれた。末永くチューニングを楽しむためには、ユーザーの負担は少ないほうがいい。
「仮に70の力だとしてもノーマルとの違いに心が躍るほど、存分に楽しめるセットアップを提供する自信があります。ユーザーには後悔せずに楽しんでほしい」
そんな思いから指山代表はオリジナルブランドである「ビオ」を2001年に生み出した。ブレーキと足をメインに特定のクルマだけに限らず、幅広いユーザーに満足してもらえる物作りを徹底している。
「R33と付き合ってきて一番の収穫は改善することの大切さを身に着けたことかもしれません。そのときは完璧だと思ってやったことも、時間が経てば技術の進化や、自分の実力や知識の向上で完璧のレベルがさらに高まる。それに柔軟に対応することが、次につながる第一歩だと信じています」
R33が教えてくれた改善の重要性はチューニングのみならずビオの製品作りにも生かされている。
(この記事は2020年6月1日発売のGT-R Magazine 153号に掲載した記事を元に再編集しています)