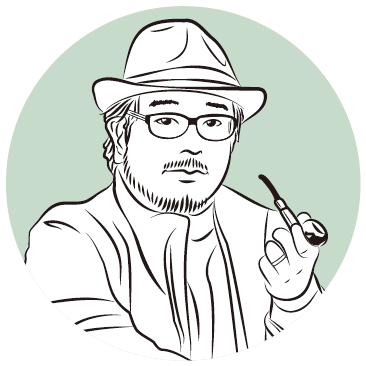個性的という言葉さえ陳腐に聞こえてしまうほどに……
この時代のシトロエンは、あらゆるモデルがじつに個性的、魅力的なスタイリングの持ち主といえよう。それは大衆向けに門戸を広げるべく開発されたGS、しかも実用本位のブレークとて例外ではなく、当時におけるコンセプトカーにも匹敵しそうなスタイリッシュな美しさに、まずは感心させられてしまう。
ドアを開いても、プラスチックとファブリックによる現代彫刻のようなインテリア。さっそくキャビンに乗り込むと、ボディ全体がいったん沈むのだが、ほどなく「スッ」と元の車高に戻る。ハイドロニューマティックの車高調節機構が、ちゃんと仕事をしているのだ。
シートはDSのごとき「人間をダメにするソファ」感はなく、意外としっかりとした表皮の張り。とはいえ、座ってみればやはりシトロエンのセオリーどおりにソフトで、しかもこのあとの疲れは最小限なものとなるのだが、それを実感したのは、すべての取材が終了したあとだった。
ところで、当初は排気量1015cc・56psでデビューしたGSの空冷水平対向4気筒SOHCエンジンは、1972年秋には1222cc・61psの「1220」も追加。さらに大改良型のGSAでは1129ccや1299ccのフラット4も搭載されたが、今回の試乗車両は1220モデル。その第一印象は、この時代の小型車としてはかなり静かでスムーズということだった。
ステアリングコラム下の、ちょっと探りにくい場所に刺したイグニッションキーを回しエンジンを始動する。左右のストロークが妙に長いシフトレバーを1速に入れて走り出すには、気遣いなどまったく不要。低速トルクが厚くて、とても乗りやすいからである。
低速域では「パルルッ」というフラット4独特の排気音よりも、「ヒューン」という空冷ファンノイズのほうが大きく聴こえてくるくらい。さらにスロットルを踏み込んで回転を上げても、むやみに排気音が高まるようなこともない。
また、わずか1220ccであるうえに、この時代のシトロエンの常として重いフライホイールが吹け上がりを緩やかにしているせいか、信号の多いわが国の道路におけるストップ&ゴーの加速も必然的に穏やかなものとなる。それでも3000rpmも回せばトルクは充分に乗ってくれるので、一般道の流れをリードするのは造作もないことである。
乗り味のすべてが特別! やっぱりハイドロ・シトロエンは素晴らしい
そして一定以上のスピードになると分かってくるのが、GSブレーク本来の資質である。空力ボディのおかげか風切り音も小さく、定速クルージングではもっと大きなサイズと排気量のクルマに乗っているかのような錯覚に陥る。
古来より「空飛ぶ絨毯」と形容されてきたサスペンションは、ハイドロニューマティックの真骨頂であるフワリと浮いたような乗り心地を提供するかたわら、ロードホールディングの点でも非常に優れている。
また、この時代には当たり前だったノンパワーのステアリングは、微速域で切り返しが続くと、情けない悲鳴を上げてしまいそうなくらいに重い手ごたえを示すいっぽう、20km/hも出ていれば劇的に軽く、しかも正確でシャープ。カーブではグラリと盛大にロールするのに、ノーズはピタリとコーナー出口を示す。
さらには4輪ディスクのブレーキも、ストロークの極端に短いハイドロ制御のシトロエン式ながら、操作に慣れれば現代車に負けないくらいにスッと効いてくれるので、あくまで無理のないスピード域であれば、まったくストレスフリーのドライビングが楽しめるのだ。
強烈に個性的なのは、今や望んでも得られなくなったシトロエンのデフォルト。でも、あくまで実用ワゴンを創ろうとした開発者側にドライバーを楽しませようだなんて意図は皆無だったはずながら、結果として極上のドライビングプレジャーを提供してくれる。
まったくハイドロ・シトロエンとは、つくづく面白いクルマであると再認識したのである。
■「旧車ソムリエ」連載記事一覧はこちら